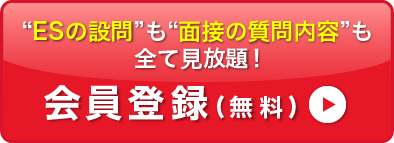エントリーシート(ES)の語尾は「ですます」?「である」?
結論、どちらでも問題ありません。
エントリーシートの語尾は「ですます調」「である調」のどちらを使っても問題ありません。絶対にこっちという決まりはありませんので、時と場合に合わせて語尾を選びましょう。 語尾をどうするかで悩んでしまうのであれば、「ですます調」をおすすめします。
どちらを選択するにせよ、それぞれメリットとデメリットがあることは理解しておき、企業やアピールしたい状況に応じて使い分けることがポイントです。
「ですます調」の特徴
「ですます調」は礼儀正しい、真面目、誠実といった印象をアピールしやすいです。
文章全体が丁寧で柔らかい印象になりやすいため、相手にマイナスイメージを与えるリスクも少ないです。しかし、控えめな印象を与えやすいため、場合によってはアピール力不足と思われることもありますが、基本的には使いやすい語調と言えます。
また「ですます調」は読みやすい反面、同じ語尾が続いて文章が単調になりやすいです。語尾に変化を持たせるのも難しいため、同じ語尾にならないように体言止めや倒置法などを上手く活用しましょう。
「である調」の特徴
「である調」は意思が強く説得力のある印象を与えることができ、インパクトのあるアピールがしやすいです。
「ですます調」を使う人が多くいる中で、「である調」を使うことで採用担当者の印象の残りやすく、アピール力を高めやすいと言えます。意思の強さをアピールしやすいため、自信を持っているように見せたい時や相手にインパクトを与えたい時には「である調」を使うと良いでしょう。
また、企業の社風に合わせて使い分けることも大切です。
例えば、個々の能力を重視するベンチャー企業の場合、柔らかさよりも自己主張をしてインパクトの強い文章にした方が、高評価される可能性があります。
ESの語尾で「ですます調」を使うメリット
①好印象を与えられる
「ですます調」を使うと、礼儀正しく丁寧な印象を与えられます。柔らかい雰囲気を出せ、マナーを守ろうとする誠実なイメージを抱いてもらえるでしょう。
②書きやすい
一般的な文末なので、「である調」よりも書き慣れています。どちらを使用するか迷ったら、一般企業では「ですます調」がおすすめです。
③読みやすい
「ですます調」を使う大きなメリットは、読み手が読みやすいと感じてくれることです。多くの人が慣れている「ですます調」を使うことで、語りかけるような文章になり、内容が伝わりやすくなります。
ESの語尾で「ですます調」を使うデメリット
①文末が単調になってしまう
「ですます調」の語尾はバリエーションが乏しく、単調になりがちです。文末が同じ表現の繰り返しにならないように、体言止めや疑問形・提案系、倒置法などを使ったりしてみましょう。
②長い文章になる
「ですます調」を使用すると文章量が多くなり、文字数を超えてしまう場合もあります。長い文章になってしまうので分かりにくくなったり、伝えたいことを書ききれなかったりします。語尾を「ですます調」で書く場合は要点を絞りながら作成しましょう。
③敬語の使い方が難しい
「ですます調」は正式には敬体といい、敬語を使う文章になる為敬体といいます。そのためエントリーシートに「ですます調」を使う場合は、敬語表現を意識しなくてはいけません。
しかし、間違った敬語を使った場合、教養がないと思われる可能性があるため注意が必要です。
ESの語尾で「である調」を使うメリット
①文字数が削減できる
「ですます調」のように敬語を意識しなくて良いため、文字数を削減することができます。例えば「考えました」と「考えた」だけでも、文字数に大きな違いがあることが分かるだろう。文字数内に収まらないと悩んでいる時にはおすすめの書き方です。
②説得力を持たせられる
「である調」は断定系のため、意思の強いイメージを与えられ、内容にインパクトと説得力を持たせることができます。読み手側からすると、自分についてしっかり確信している・理解している人だとイメージするため、自信と信頼感を感じることができます。
ESの語尾で「である調」を使うデメリット
①堅い印象を与える
「である調」は主にレポートや論文のような文章に使用する書き方のため、読み手に堅い印象を与えてしまいます。採用担当によっては人柄が理解しづらいと思う場合もあるため、使用する際は「ですます調」よりも内容に齟齬が無いか確認する必要があります。
②高圧的に感じる
表現次第では上から目線だと思われてしまうため、読み手に高圧的な印象を与える場合があります。書き終えたら必ず文章をチェックし、読み手にマイナスなイメージを与えないか確認しましょう。その際、第三者にも見てもらうことで、より正確に確認することが出来るのでおすすめです。
内容がしっかりしていなければ生意気な印象を与えることもあるので、文章構成・エピソードなどにも問題がないかのチェックも欠かさず行いましょう。

効果的な句読点の活用法
「読みやすい文章を書くこと=相手(読み手)への配慮ができる」ということです。エントリーシートを書く上で読みやすさを意識することは、非常に重要なポイントとなります。そのためには句読点を効果的に活用することが大切です。句読点の使い方にはいくつかのポイントがあります。
読点の活用ポイント
①50文字の文中に1~2つの読点を入れる
これが文章の黄金比だと言われています。意識して入れてみることで、読みやすい文章になります。
②重文・複文の区切りに入れる
1つの文章に「主語+述語」のかたまりが複数あるものを、「重文」または「複文」といいます。
③接続詞・副詞のあとに入れる
接続詞:しかし、また、あるいは
副詞:なぜなら、もし、決してなど
④長い主語の後に入れる
通常、読点は文章の「主語」「主題」の後に打つのがルールとなっています。特に、長い主語の後に読点を打つことで、「ここまでが主語ですよ」と読み手に伝えることができます。
⑤並列関係にある単語の区切りに入れる
単語を並べる際、読点を使うパターンと「・」を使うパターンの2種類が考えられますが、特に決まりはありません。相手の読みやすさに配慮しつつ、文書内では統一することを意識しましょう。
句点の活用ポイント
①かっこの後に入れる
文章の最後に()を使う場合、句点はかっこの後に打ちましょう。
②かっこの前に打つ例外もあります
参照元や筆者名などを文章の最後に記載する際は、かっこの前に句点を打つ場合もあります。
好印象なエントリーシートの書き方
①重要ポイントは語尾を統一させること
「ですます調」「である調」のどちらを使用するにしても、エントリーシートの語尾は必ず統一しましょう。混ぜて使ってしまうと、文章がまとまっていないように見えるため、マイナスな印象に繋がってしまいます。また、語尾が揃っていないと読みづらくなり、読み手にストレスを与えてしまいます。
どちらかを選んだらその項目内では語尾を統一して記載しましょう。
②何よりも内容が最重要
エントリーシートの語尾よりも重要なのは内容です。書き方を工夫すれば印象を良くすることはできますが、内容が良くなければ好印象を与えることはできません。
評価の大部分を握っているのは内容なので、まずは内容をしっかり練り上げることを意識してみましょう。
しかし、中にはエントリーシートに書く内容が思いつかない、具体的なエピソードがない、という人がいるようです。そういった場合は、自己分析がきちんとできていない可能性があります。まずは自分の過去を様々な角度から振り返ってみましょう。
③正しい書き言葉で統一する
書き方については、大前提のルールを守らなければ常識がないと判断され、少なからずマイナスのイメージを与えてしまいます。文章を書くのに慣れていない学生は、書き言葉が間違っていないか確認するのも大切です。
例:御社→貴社、食べれる→食べられる(ら抜き言葉)、してる→している(い抜き言葉)
まとめ|語尾は統一性が大事
エントリーシートでは、「ですます調」「である調」のどちらを使っても問題ありません。しかし、企業や書く内容によって使い分けることが大切です。それぞれの語尾のもつメリットとデメリットを考慮した上で選ぶといいでしょう。
もちろん、どちらを使うにしても、語尾を統一させることが重要です。そして、何よりも重要なのはエントリーシートに書かれている中身や内容であるということを忘れてはいけません。
就活ノートに登録すると以下の特典がご利用になれます!
- ・就活に役立つメールマガジンが届きます。
- ・企業の選考情報の口コミ、通過エントリーシートが見放題になります。
- ・会員限定公開の記事が読めます。
- ・会員専用機能が利用できます。(お気に入り登録など)
全て見放題!
会員登録(無料)